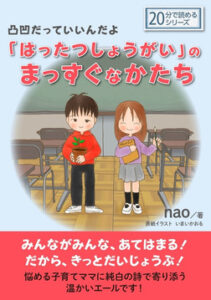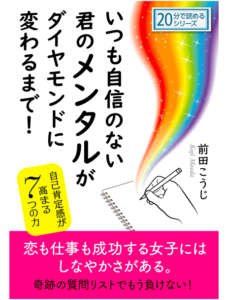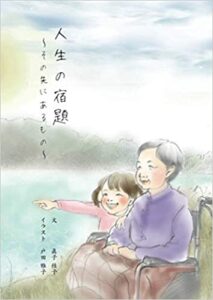一般用医薬品の大部分をライセンスによって販売できる国家資格「登録販売者」。このブログでは、登録販売者試験に合格するために必要な知識を紹介しています。
くすりは人体にとって異物であり、リスクを伴っています。そのため、人体の働きと医薬品についてよく理解し、購入者に正しく情報を伝えることが大切です。
今回は登録販売者試験の第2章を確認テスト形式で学んでいきます。
1.消化液による消化は機械的消化という。
× 消化液は化学的消化
2.歯冠の表面は象牙質で覆われ、体で最も硬い部分となっている。
× エナメル質
3.舌は味覚を感知するほか、咀嚼された飲食物を攪拌してすい液と混和させる。
◯
4.舌の表面は、味蕾という無数の小さな突起があり、味覚を感知する部位である舌乳頭が分布している。
× 無数の小さな突起は舌乳頭、味蕾は味覚を感知する部位
5.すい液線から分泌されるすい液にはデンプンをブドウ糖に分解するコール酸が含まれる。
× コール酸ではなくプチリアン(すい液アミラーゼ)
6.すい液は味覚の形成にも重要な役割を持っている。
◯
7.すい液にはタンパク質を分解するトリプシンが含まれている。
× デンプンをデキストリンや麦芽糖に分解する消化酵素が含まれている。
8.すい液に含まれるリゾチームには、細菌の細胞壁を分解する酵素作用および消炎作用がある。
◯
9.すい液は、殺菌・抗菌物質が含んでおり、口腔粘膜の保護・洗浄。殺菌などの作用もある。
◯
10.食堂は喉元から上腹部のみぞおち近くまで続く、直径1〜2cmの管状の器官で消化液の分泌腺はない。
◯
11.咽頭は、口腔から食道に通じる食物路と、呼吸器の気道が交わるところである。
◯
12.食道には、消化液の分泌腺がある。
× 消化液の分泌腺はない。
13.胃の内壁は粘膜で覆われており、粘膜の表面にある無数の孔からは塩酸(胃酸)やペプシンを分泌している。
× ペプシノーゲン
14.胃の内容物の滞留時間は、脂質分の多い食品より炭水化物主体の食品の方が比較的長い。
× 炭水化物の食品の方が短い
15.小腸は、トリプシノーゲンをトリプシンにする。
◯
16.小腸のうち十二指腸に続く部分の概ね上部40%が空腸、残り60%が回腸である。
◯
17.血糖値を調節するホルモン(インスリン・グルカゴン)は肝臓から血液中に分泌される。
× 肝臓でなはく膵臓
18.膵臓は消化腺であるとともに、血糖値を調節するホルモンなどを血液中に分泌する内分泌腺でもある。
◯
19.すい液に含まれる酵素には、炭水化物およびタンパク質を分解する酵素はあるが、脂質を分解する酵素は含まれていない。
× 脂質を分解する酵素は含まれている(リパーゼ)
20.胆汁に含まれる胆汁酸塩は、炭水化物の消化を容易にし、また脂溶性ビタミンの吸収を助ける。
× 炭水化物ではなく脂質の消化を容易にする。
21.腸内に放出された胆汁酸塩の大部分は、再吸収されず体外に排出される。
× 再吸収されて循環する。
22.胆汁に含まれるビリルビンは血液中のコレステロールが分解されて生じた老廃物である。
× コレステロールではなくヘモグロビン
23.胆のうは、肝蔵で産生された胆汁を濃縮して蓄える器官で、十二指腸に内容物が入ってくると収縮して腸管内に胆汁を送り込む。
◯
24.黄疸とは、ヘモグロビンが胆汁中へ排出されず血液中に滞留して、皮膚や白目が黄色くなる現象である。また、過剰なヘモグロビンが尿中に排出され、尿の色が濃くなることもある。
× ヘモグロビンではなくビリルビン
25.肝臓は、大きな臓器であり、胸骨の後方に位置する。
× 横隔膜の下
26.小腸で吸収されたグリコーゲンは、血液によって肝臓に運ばれてブドウ糖として蓄えられる。
× 小腸で吸収されたブドウ糖は、血液によって肝臓に運ばれてグリコーゲンとして蓄えられる。
27.肝臓に蓄えられたグリコーゲンは、血糖値が下がったときなど、必要に応じてブドウ糖に分解されて血液中に放出される。
◯
28.肝臓は、脂溶性ビタミンであるビタミンA、D等を貯蔵することはできるが、ビタミンB6やB12等の水溶性ビタミンは貯蔵することができない。
× 水溶性ビタミンも貯蔵できる。
29.アルコールは、肝臓へ運ばれて酢酸に代謝されたのち、さらに代謝されアセトアルデヒドになる。
× アセトアルデヒドに代謝されたのち酢酸になる。
30.アルコールは、胃や小腸で吸収されるが、肝臓へと運ばれて一度酢酸に代謝されたのち、さらに代謝されてアセトアルデヒドになる。
× アセトアルデヒドに代謝されたのち酢酸になる。
31.肝臓では、必須アミノ酸が生合成される。
× 必須アミノ酸は体内で生成されない。
32.肝臓は、コレステロール、フィブリノゲンなどの生体物質の産生する。
◯
33.大腸は、盲腸・虫垂・上行結腸・横行結腸・下行結腸・S状結腸・直腸からなる管状の臓器で、内壁粘膜に絨毛がない。
◯
34.大腸の粘膜から消化液が分泌され、消化が活発に行われている。
× 大腸に消化液の分泌腺はない。
35.通常、糞便はS状結腸には滞留しない。
× S状結腸ではなく直腸
36.大腸で水分と電解質の吸収が行われている。
◯
37.大腸内の腸内細菌が食物繊維を発酵分解して生じた栄養分は、粘土上皮細胞の活動に利用される。
◯
38.大腸の粘膜から分泌される粘液は、便塊を粘膜上皮と分離しやすく滑らかにする。
◯
39.糞便の成分の大半は水分で、次に多いのが食物の残滓であり、そのほかに腸内細菌の死骸などが含まれている。
× 腸壁上皮細胞15〜20%、腸内細菌10〜15%、食物残滓5%
40.盲腸は、大腸の週末の部分に位置し肛門へと続いている。
× 盲腸ではなく直腸の説明
41.大腸が正常に働くには、腸内細菌の存在が重要である。
◯
42.大腸の腸内細菌は、血液凝固や骨へのカルシウム定着に必要なビタミンK等の物質も産生している。
◯
今回はここまで。続きは、vol.9でお伝えします。
この記事を読んだ方はこちらの講座も閲覧しています
| おすそわけマーケットプレイス「ツクツク!!」 | |
 | 価格:20,000円 |
| おすそわけマーケットプレイス「ツクツク!!」 | |
 | 価格:11,000円 |
| おすそわけマーケットプレイス「ツクツク!!」 | |
 | 【マスターコース2時間×3回】●カラーレイキ講座 セルフケア部門 埼玉県坂戸市 出張可能 価格:77,000円 |