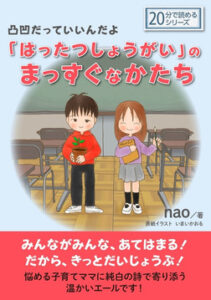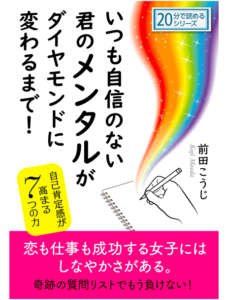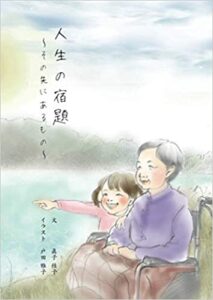一般用医薬品の大部分をライセンスによって販売できる国家資格「登録販売者」。このブログでは、登録販売者試験に合格するために必要な知識を紹介しています。
くすりは人体にとって異物であり、リスクを伴っています。そのため、人体の働きと医薬品についてよく理解し、購入者に正しく情報を伝えることが大切です。
前回に引き続き、登録販売者試験の第2章を確認テスト形式で学んでいきます。
1.医薬品には、吸収された有効成分が循環血液中に移行して全身をめぐって薬効をもたらす全身作用と、特定の身体部位において薬効をもたらす局所作用がある。
◯
2.内服薬の成分は、消化管で濃度の薄い方から濃い方へ拡散し、吸収される。
× 濃い方から薄い方へ
3.消化管から医薬品の吸収は、消化管が消化作用によって積極的に医薬品成分を取り込むことで起こる。
× 拡散によってしみ込んでいく。
4.内服薬には、錠剤、カプセル剤、腸溶性製剤等があるが、多くの場合、小腸で有効成分が溶出する。
× 腸溶性製剤以外は胃で溶出する。
5.全身作用を目的として使用された坐剤の有効成分は、吸収されると初めに肝臓で代謝された後、血流に乗って全身を巡る。
× 直腸から吸収された場合は肝臓を通らない。
6.坐剤は、医薬品の成分が吸収され、肝臓で代謝を受けてから全身を巡る。
× 坐剤は肝臓を通らない。
7.点鼻薬は、医薬品の成分が吸収され、肝臓で代謝を受けてから全身を巡る。
× 鼻粘膜から吸収された場合、肝臓を通らない。
8.皮膚に適用する医薬品は、加齢等により皮膚のみずみずしさが低下すると、医薬品の成分が浸潤・拡散しやすくなる。
× 浸潤・拡散しにくくなる。
9.貼付剤は、医薬品の成分が吸収され、肝臓で代謝を受けてから全身を巡る。
× 皮膚から吸収されると肝臓を通らない。
10.皮膚に適用する医薬品の有効成分が皮膚から浸透する量は、皮膚の状態や傷の有無などの影響を受けることなく、常に一定である。
× 皮膚の状態で影響を受ける。
11.小腸から吸収された医薬品のほとんどは、、血液脳関門を経由して肝臓に入り代謝を受けてから全身をめぐる。
× 血液脳関門ではなく門脈
12.医薬品の成分は、血液中で血漿タンパク質と結合した複合体を形成し、複合体を形成している分子には酵素が作用しないため、一度に代謝されてしまうことはほとんどない。
◯
13.循環血液中に移行した医薬品の成分のほとんどは、未変化体またはその代謝物として糞便中に排泄される。
× 糞便ではなく尿
14.循環血液中に移行した医薬品の成分は、主として肝細胞内の酵素系の働きで代謝を受ける。
◯
15.医薬品成分と血漿タンパク質との結合は速やかかつ不可逆的である。
× 可逆的
16.複数の医薬品を併用したときは、結合するタンパク質を医薬品成分の分子どうしが互いに奪い合って、複合体を形成していない分子の割合が増す。
◯
17.腎臓の機能が低下した状態にある人では、医薬品の成分が速やかに排泄されてしまい、循環血液中に存在する時間が正常の人よりも短くなるため、効き目が弱くなる。
× 腎機能が弱っていると排泄が遅れる
18.医薬品の成分の排泄は専ら尿により行われ、糞便中に混じって排泄されることはない。
× 糞便や乳汁からも排泄される
19.循環血液中に移行した有効成分は、多くの場合、標的となる細胞に存在する受容体、酵素、トランスポーターなどのタンパク質と結合し、その機能を変化させることで薬効を現す。
◯
20.医薬品が摂取された後、成分の吸収が進むに連れてその血中濃度が上がり、最高血中濃度を超えたときに生体の反応として薬効がもたらされる。
× 最小有効濃度
21.十分な間隔をあけずに追加摂取するなどして医薬品の血中濃度を高くしても、あう濃度以上になるとより強い薬効は得られなくなり、有害な作用も現れにくくなる。
× 有害な作用も現れやすくなる。
22.医薬品が摂取され、その有効成分が循環血液中に移行すれば、その血中濃度に関わらず生体の反応としての薬効が現れる。
× 一定以上の濃度が必要
23.一度に大量に医薬品を摂取したり、十分な間隔をあけずに追加摂取したりして血中濃度を高くしても、ある濃度以上になると強い薬効は得られなくなる。
◯
24.全身作用を目的とする医薬品は、血中濃度が無効域と危険域の間の範囲となるよう使用量や使用間隔が定められている。
◯
25.有効成分を吸収させ、全身に分布させることにより薬効をもたらすための錠剤として、錠剤、散財、経口液剤、外用液剤などがある。
× 外用液剤は全身作用を期待するものではない。
26.経口液剤は、一般的に固形製剤と比べ、服用後、循環血液中の成分濃度が上昇しやすい。
◯
27.錠剤(内服)は、胃や腸で崩壊し、有効成分が溶出することが薬効出現の前提となるため、例外的な場合を除いて、口中で噛み砕いて服用してはならない。
◯
28.口腔内崩壊錠は、口の中の唾液で速やかに溶ける工夫がなされているため、水なしで服用することができる。
◯
29.経口液剤は、固形製剤に比べ、飲み込みやすいが消化管からの吸収は比較的遅い点が特徴である。
× 吸収は早い
30.チュアブル錠は、口の中で舐めたり、噛み砕いたりして服用してはいけない。
× 噛み砕いたり水無しでもOK
31.顆粒剤は粒の表面がコーディングされているものもあるので、噛み砕かずに水などで服用する。
◯
32.カプセル剤の原材料として広く用いられているゼラチンはブタなどの動物由来のタンパク質であるため、アレルギーを持つ人では使用を避けるなどの注意が必要である。
◯
33.外用局所に適用する剤形のうち、一般的に適用部位を水から遮断した場合にはクリーム剤ではなく軟膏剤を用いることが多い。
◯
34.外用液剤は、軟膏剤やクリーム剤に比べて、適用した表面が乾きやすく適用した部位に直接的な刺激感などは与えない。
× 直接的に刺激を与える
35.軟膏剤とクリーム剤を比べると、一般的に幹部が乾燥していたり、幹部を水で洗い流したい場合は、軟膏剤を用いることが多い。
× 幹部を水で洗い流したい場合は、クリーム剤を用いることが多い。
36.貼付剤は皮膚に粘着させて用いる剤形であり、適用した部位に有効成分が一定期間留まるため、薬効の持続が期待できる反面、適用部位においてかぶれなどが起こる場合がある。
◯
37.外用液剤は、有効成分を霧状にするなどして、局所に吹き付ける剤形であり、手指では塗りにくい部位や広範囲に適用する場合に適している。
× スプレー剤の説明
今回はここまで。続きは、vol.13でお伝えします。
この記事を読んだ方はこちらの講座も閲覧しています
| おすそわけマーケットプレイス「ツクツク!!」 | |
 | 価格:20,000円 |
| おすそわけマーケットプレイス「ツクツク!!」 | |
 | 価格:11,000円 |
| おすそわけマーケットプレイス「ツクツク!!」 | |
 | 【マスターコース2時間×3回】●カラーレイキ講座 セルフケア部門 埼玉県坂戸市 出張可能 価格:77,000円 |