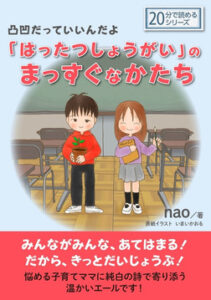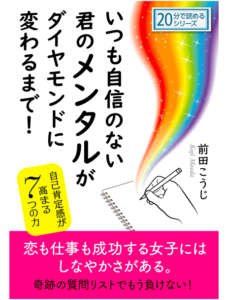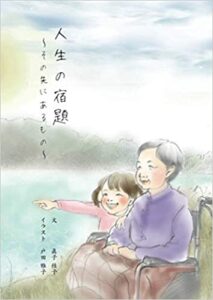一般用医薬品の大部分をライセンスによって販売できる国家資格「登録販売者」。今日からこのブログで、登録販売者試験に合格するために必要な知識を紹介していきます。
くすりは人体にとって異物であり、リスクを伴っています。そのため、まずは医薬品の本質をよく理解し、購入者に正しく情報を伝えることが大切です。
また、薬を適正にしようしていただくための基本知識として、薬害の歴史を確認テスト形式で学んでいきます。
1.医薬品が人体に及ぼす作用は複雑かつ多岐にわたるが、そのすべてが解明されている。
× すべては解明されていないので、何が起こるかわからない。
2.医薬品は、期待される有益な効果(薬効)のみをもたらす。
× 副作用もある。
3.製造販業者から提供される製品回収等の情報に、日ごろから留意しておく必要がある。
◯
4.医薬品は、人の疾病の治療のみに使用される。
× 診断や予防も含む。
5.人体に対して直接使用されていない医薬品は、人の健康に影響を与えない。
× 殺虫剤などを誤って使うと健康被害がある。
6.医薬品は、市販後にも医学・薬学などの新たな知見、使用成績などに基づき、その有効性、安全性などの確認が行われる仕組みになっている。
◯
7.登録販売者は、常に医薬品の有効性、安全性等に関する新しい情報の把握に努める必要がある。
◯
8.医薬品は、人の生命や健康に密接に関連するものであるが、高い水準で均一な品質は保証されていない。
× 保証されていなければならない。
9.医薬品医療機器等法では、健康被害の発生の有無にかかわらず、医薬品に異物等の混入、変質等があってはならない旨が定められている。
◯
10.医薬品の効果とリスクは、薬物曝露時間と曝露量との和で表現される(用量ー反応関係に基づいて評価される)。
× 和ではなく積(掛け算)
11.医薬品の投与量と効果の関係は、薬物用量を増加させるに伴い、効果の発現が検出されない「無作用量」から、最小有効量を経て「治療量」に至る。
◯
12.毒性の指標として用いられるLD50は、動物実験における50%致死量のことである。
◯
13.少量の医薬品の投与では、発がん作用、胎児毒性や組織・臓器の機能不全を生じることがない。
× 少量であっても可能性がある。
14.治療量を超えた量を超えた単回投与した後に毒性が発現する恐れが高いことは当然であるが、少量の投与でも長期投与されれば慢性的な毒性が発現することもある。
◯
15.新規に開発される医薬品のリスク評価は、医薬品開発の国際的な標準化(ハーモナイゼーション)制定の流れの中で実施されている。
◯
16.新規に開発される医薬品のリスク評価は、非臨床試験における安全性の基準であるGLP(Good Laboratry Practice)に準拠して実施されている。
◯
17.ヒトを対象とした臨床試験における効果と安全性の評価基準には、国際的にGLP(Good Laboratry Practice)が制定されている。
× ヒトを対象としたものはGCP(Good Clinical Practice)。医薬品は市販前に多くの検査が実施されている。
18.製造販売後の調査および試験の実施基準の英語略称はGVPで表す。
× GVPは製造販売後の安全管理基準(Good Vigilance Practice)
19.医薬品に対しては、製造販売後の調査および試験の実施基準としてGPSP(Good Post-marketing Studay Practice)が制定されている。
◯
今回はここまで。続きは、vol.2でお伝えします。
この記事を読んだ方はこちらの講座も閲覧しています
| おすそわけマーケットプレイス「ツクツク!!」 | |
 | 価格:20,000円 |
| おすそわけマーケットプレイス「ツクツク!!」 | |
 | 価格:11,000円 |
| おすそわけマーケットプレイス「ツクツク!!」 | |
 | 【マスターコース2時間×3回】●カラーレイキ講座 セルフケア部門 埼玉県坂戸市 出張可能 価格:77,000円 |